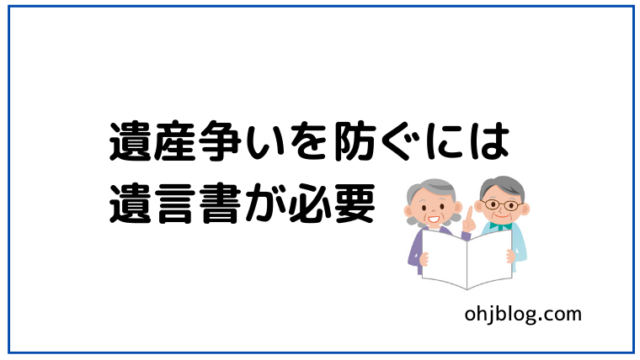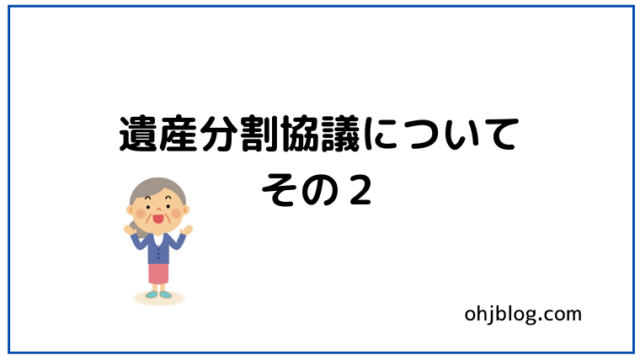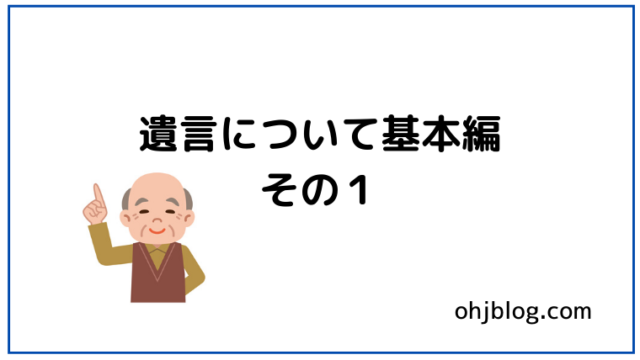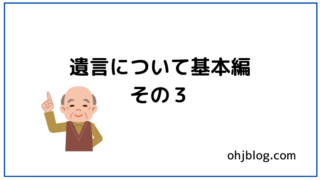これまで4回にわたって遺言の基本的なことを解説してきました。今回は遺留分制度について解説します。後半は、遺言のまとめとして、遺言者が亡くなった場合に取るべき行動について解説します。
遺留分制度について
一定範囲の相続人に対して被相続人(遺言者)の財産の一定割合につき相続権を保障するもので,被相続人(遺言者)がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合は,相続人は侵害された遺留分に応じた金銭の支払請求をすることができます。
遺留分は相続財産に対する最低限の保障ということになります。そこで,遺留分は「正義の味方」とも言われています。
①遺留分を有する者とその割合について
遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は,配偶者,子,直系尊属(父・母等)で「兄弟姉妹には遺留分はありません」(民法1042条)
その趣旨は,残された子供ら家族の生活を守る必要はありますが,兄弟姉妹はもともと生計が別々であることから,あえてその人達の生活まで守る必要はないという考え方だと思います。
遺留分の割合は,「相続財産全体に対する割合」として定められており,相続人が配偶者のみ・配偶者と子供・配偶者と直系尊属・子供のみ場合には2分の1,また相続人が直系尊属のみの場合には3分の1です。
この割合に「各自の法定相続分をかけたもの」が各自の遺留分となります。
仮に,相続人が妻,子供ABCの3人ならば,妻の遺留分の割合は1/2×1/2(法定相続分)=1/4で,子供ABCのそれぞれの遺留分の割合は1/2×1/6(法定相続分)=1/12です。
例えば,父が全ての財産(1200万円)を第三者に遺贈したため相続人への相続がなかった場合において,上記遺留分の割合で計算すると,相続人の妻は1200万円×1/4=300万円,子供らは1200万円×1/12=各自100万円(計300万円)となります。
これらの遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを,亡き父から遺贈を受けた第三者に請求することができます(民法1046条)
②遺留分侵害額請求権の期間の制限
この請求権は,遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。
また,遺留分が侵害されていることを知らなくても,相続開始のときから10年経過するとこの請求権は消滅します(民法1048条)。
遺言について 総まとめ
次は,これまで説明した相続・遺言についての総まとめです。「父が突然に亡くなった」ことを前提として,相続人代表者としての長男が相続に関して対応すべきことを,相続に関する手順に沿って説明します。
長男が最初にやらなければならないこと
相続は被相続人(父)の死亡により開始するので,長男はまずは次のことを確認した上,以下の手順に従って対応します。
自筆証書遺言が自宅等にあるいは法務局に保管していないかどうか確認,公正証書遺言を作成していないかどうか確認する。
プラスの財産を確認するとともに,マイナスの財産(債務の有無)も確認する。
先妻や養子の有無なども併せて確認する。
自筆証書遺言も公正証書もなかった場合
相続人全員で遺産分割協議を行う(協議が整わないときは家庭裁判所に調停を申し立て解決を図る方法がある)。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成(相続人の署名・押印)する。
この遺産分割協議書により遺産分けの手続を行う。
自筆証書遺言があった場合
家庭裁判所の検認を受ける。 → 検認手続終了 → その遺言により遺言の内容を執行(実行・実現)する。
家庭裁判所の検認は不要なので,その遺言により遺言の内容を直ちに執行(実行・実現)する。
公正証書遺言があった場合
公証人から交付された公正証書遺言の正本又は謄本により遺言の内容を直ちに執行(実行・実現)する。
以上のとおり,私がこれまで説明してきた相続や遺言の話をコンパクトに取りまとめた内容となっていますので,相続が発生した場合における相続人らの対応方も含めまして,今後の相続等の際に参考としていただければ幸いです。